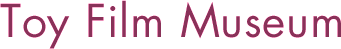2018.05.23infomation
「新野敏也のレーザーポインター映画教室第3弾」のレポート(6)
【第二部:キートンのアクロバットと特殊撮影を探究!】その2

(A)

(B)
「即席百人芸」(別題:一人百役)The Playhouse 前篇《特撮について》
1921年 コミック・フィルム・コーポレーション=メトロ・ピクチャーズ作品(アメリカ)
製作:ジョゼフ・M・スケンク、監督:バスター・キートン、エディ・クライン
撮影:エルジン・レスリー、美術:フレッド・ガブリー
出演:バスター・キートン、ジョー・ロバーツ、ヴァージニア・フォックス
伴奏:谷川賢作(キーボード)、太田惠資(ヴァイオリン)
※2016年4月16日(土)エスパス・ビブリオ
「喜劇映画のビタミンPART3 メロディが語る映画」の公演より
日本語字幕:石野たき子
本作は「隣同志」と比べると、同じキートン発案による喜劇でも、対極に位置するくらいの異色作です。未見の方へストーリーを説明するにも、僕自身がストーリーの説明すらできないようなラフな構成の短編です。シークエンス(エピソード)ごとに見るとスゴく面白い作品ながらも、ストーリーに一貫性がなく散漫で、かなりブッ飛んだ印象を受けます。
大雑把にその構成を分けると、《多重露光でのトリックによるキートンだらけの独演会》と《舞台の裏方キ-トンがミス連発》と《双子の姉妹の片方に恋心を寄せるキートン青年》の三つのプロットとなります。この三つを強引に組み合わせたことは明らかで、おそらく前半のトリック撮影を実現したくて製作を始めて、あとから思いついたプロットを組み合わせて作品にしたのでは?と考えました。僕のこの仮説は、ギャグ構成とストーリー展開の順序で《つじつまの合わない部分》を見つけたことで思いつきました。
以下、順を追って説明しますので、その《つじつまの合わない部分》ついては後回しになりますことをどうかご了承下さい。まずは、最初のプロット(シークエンス)であり、本作の超目玉となります《多重露光でのトリックによるキートンだらけの独演会》について、どれくらいスゴイ偉業なのかを説明します。
未見の人のお楽しみを考慮して詳しい内容は省きますが、このシークエンスは、とにかく派手!キートンが一画面中に一人で何役も演じる合成が超目玉です!これはマスク合成という初歩的な撮影トリック(多重露光)を応用しております。撮影手順の一例を挙げると、3秒間の《二人のキートンが並んで踊る》場面は、カメラのレンズの右側半分を黒布などで覆い(マスク=フィルム左側だけ感光させる)一人目を撮影、フィルムを3秒巻戻し、今度はレンズ左側半分を覆い(フィルム右側だけ感光させる)、同じ踊りを3秒撮影、そしてこのフィルムを現像すると《二人のキートンが並んで踊る》トリックが完成となります。この説明だけですとトリック自体は単純に思えるでしょうけど、本作はキートンが緻密な計算で、レンズのマスク分割数と再度撮影する回数を増やして、同一人物によるオーケストラやミンストレル・ショーを華やかに披露します。何よりも注目すべき点は、このトリックの精度です。
キートンはジョルジュ・メリエスの『一人オーケストラ(L'Homme-orchestre)』という1900年発表の短編から、この多重露光トリックのギャグを拝借したという説もあります。因みにメリエスの場合は、ギャラの支払い状況から出演者がみんな逃げちゃったので、自分独りで演じなければならなくなったという都市伝説みたいな話もありましたが、本当かどうだかわかりません。しかし、たとえキートンがメリエスの技法を模倣したのであっても、本作『即席百人芸』のトリックを生み出したエネルギーは、メリエスの創作意欲をはるかに凌駕しているとハッキリ断言できます。
そのトリックの精度を語る前に、まずは本作のトリック開発に関与した人物も紹介しなければなりません。この映画の撮影者は、エルジン・レスリー(1833~1944)という人物です。レスリーは、メリエスのアメリカ支社(スター・フィルム)を経て、マック・セネット門下のロスコー・アーバックル作品の撮影担当になり、それからキートン作品の専属カメラマンとなりました。それ故、キートン自身が考え出したオリジナルの案に、多重露光のマスク合成など、何かしらのアドバイスをした可能性も考えられます。レスリーは、映画界へ転向して間もないキートンにアーバックルの撮影所内で、カメラのメカニズムや写真化学などフィルムの特性を教えたそうですので、本作におけるトリックはキートンとレスリーの共同開発と考えても間違いはないでしょう。
それでは、キートンとレスリーが行なったトリック=マスク合成の精度について検証します。8ミリや16ミリのフィルムを使って同様のトリックをやったことがある人でしたらご存知かもしれませんが、まずマスク合成を行なうと、画面内の水平な部分がやや縦にズレます。これはカメラの構造上、避け難い欠点なのです。また、複数の人物(同じ人が演じる)が同一画面上で踊りや演技をすると、相当な訓練をしない限りは動きに若干のズレが生じてしまいます。ところが、百年くらい前に作られた本作のマスク合成は、複数のキートンの演技がピッタリとシンクロしていて、おまけに水平部分にズレもありません(これはステージの縁などで確認できます)!とにかくマスク合成には見えず、右と左に並ぶソックリな役者二人がピッタリと息を合せてステージ上で踊っているだけ(写真A)にしか見えません!この精度こそが本作の一番の肝!エルジン・レスリーとキートンによる革新的で、驚異的な知識によって構成された成果物なのです。
技術的な説明をしますと(おもちゃ映画ミュージアムへご来場の方はおそらくご存知でしょうけど)、皆さんのご覧になるスクリーンの画は、フィルムという帯へ縦に配列されたものです。この配置された画が、無声映画の時代では1秒間に16枚(現在は24枚)の速度で、シャッターを介してパラパラ漫画のように繰り出されることから動画に見える訳です。これを《間欠運動》と呼びます。映画カメラや映写機は、長いフィルム(帯)に並ぶ画の両脇へ等間隔に開けた穴(パーフォレーション)を金属製の爪で引っかけて、上から下へと順次シャッター前を通過させる仕組みになっておりまして、このメカニズムによって間欠運動が正確に構成されるのです。
19世紀末にエジソンやリュミエール兄弟が映画を発明した当初から、このメカニズムは今日までほとんど変わらないままですが、物理的な欠点も変わらないまま残っております。それは《穴を金属製の爪で引っかけて、上から下へと順次シャッター前を通過させる仕組み》に起因するもので、画面に若干の縦ユレ(微振動)が発生することが避けられません。フィルムを《上から下へ》運行するのは重力に従って自然な流れですが、機械的に画を1コマずつ《金属製の爪で引っかけて》動かすため、微振動が必然的に起こります。この微振動は、スクリーンで見ている限り気づかない程度のものですが、マスク合成(多重露光)などを行なう場合、合成した部分で顕著にズレが識別できてしまうのです。
ところが、キートン作品の合成には、このようなズレがまったく見られません。百年くらい前なのに精度が高すぎる!スゴすぎる!と僕は感心して、もしや使用した撮影機材に秘密があるのでは?とアタリを付けて調べたところ、予想通りにミッチェルというカメラが使われておりました。
ミッチェルは、フィルム(画)の微振動を解消するため、レジストレーション・ピン(通称レジピン)という機構を装備したカメラです。このレジピンは、フィルムを運行する《金属製の爪》とは別に、シャッターに連動して固定ピンが飛び出す仕組みで、爪とピンによってフィルムの両側の穴を1コマずつガッチリ据え付けます。つまり画面を安定させるための画期的なメカニズムなのです。さらにこのカメラは、可変式のシャッター(本体外側のツマミを回すとシャッターの開き具合が変わる)やフィルムの使用量がコマ単位でわかる(道路の通行量調査でカチカチ使うような)デジタル表示のカウンターも装備されております。このシャッターの開き具合(シャッター開角度)やフィルムの使用量がわかるカウンターを応用すると、旧来は現像所でフィルムに薬品を塗付する加工処理となっていたフェード・イン(暗転)、フェード・アウト(明転)や、この二枚のフィルムを重ねて再現像するオーバー・ラップ(またはディゾルブとかクロス・フェードと呼ぶ=前のシーンから後のシーンへとだんだん交差して変わる)が撮影時でも可能となる訳です。そんなミッチェルの高機能をキートンとエルジン・レスリーは熟知して、早々と応用していたことに、僕は脅威を感じました!
元々このカメラは、1917年に発売された直後、最新鋭機材の大好きなマック・セネットが、自社キーストンのロスコー・アーバックル撮影班に買い与えていたものでした。アーバックルがキーストン社から独立して新しいプロダクションを設立した際、同道したカメラマンのレスリーもミッチェルを採用したことで、レスリー=キートン=ミッチェルの関係が構築されたのでしょう。ちょうど本作『即席百人芸』製作の頃、ミッチェル・カメラ・コーポレーションは改良を重ねてレジピンや可変シャッターの特許を取得していたので、飽くまで僕の妄想かもしれませんが、ひょっとするとキートンの撮影現場からの希望や意見を、ミッチェル側が開発にフィード・バックしてかもしれませんね。
余計な話ですが、ミッチェルというカメラは、日本で土井製作所という精密機器メーカーが複製品(通称ドイ・ミッチェル)を製造販売しますが、レジピンのパテント料が高額なために、この機能だけが省かれておりました。尚、『レーザー・ポインター映画教室』の開催当日では、このレジピンを僕が口頭だけで説明して、ご来場の皆さんが???と感じていたところ、何と!おもちゃ映画ミュージアムの太田教授が、分解されたミッチェルからレジピン付きのシャッター部分(現物)を取り出して補足して下さいました!この拙文をお読みになって、より深くミッチェルについてお知りになりたい方は、是非、おもちゃ映画ミュージアムを訪れてみて下さい!
話がだいぶ逸れてしまいましたが、キートンとレスリーは、このミッチェルの機能によって、正確に画面のズレがなく合成、ピッタリとコマ単位で演技を同調させていた訳です。その撮影の際にキートンは、演技(踊り)やカメラを回すタイミングを、バンジョー奏者に曲を弾かせてスピード(拍子)を合せていたとされます。ついでに恐ろしい話ですが、当時のカメラは手回しだったのです!推測するに、フィルム・カウンター(目盛り)でコマ数と演技を計りながら1回目の撮影を行ない、ピッタリ同じコマ数のフィルムを巻き戻して2度目の撮影(合成)、その際にはバンジョー奏者のリズムと共にフィルム・カウンターのコマ数カッチリに振り付けを演じていたのでしょう。
ここでもう一人、技術的な功労者を加えさせて頂きます。本作を製作していた時代では、「照明技師」という撮影現場においてカメラマンと共に映画を構築するためのアーティスト=職匠は、まだ確立されておりませんでした。「照明」に該当するスタッフは、カメラマンや美術(大道具)の助手となる位置づけで、「エレクトリック・エンジニア」なる裏方さんとしてタイトルにクレジットされていたのです。本作『即席百人芸』では、フレッド・ガブリー(1881~1951)という人が美術担当と照明を兼任して、「エレクトリック・エンジニア」という役職になっておりました。ガブリーは本稿でマスク合成の精度を語るうえでは、キートン、レスリーに並ぶくらいの相当な貢献をしていたと僕は思います。マスク合成における照明の見事な技量もさることながら、もしかしたらガブリーは、レスリーのカメラ横でフィルム使用量のカウンター目盛りを確認しつつ、キートンへ指示を出していたのでは?とも想像しております。
今日ではCGなどで、何の画面をベースに何のレイヤーをいくつ重ねるか決めれば、簡単に(?)合成画面ができてしまいますが、映画がフィルム主流だった1990年代前半までは、苦労を重ねて撮影したフィルムを現像してから、初めてマスク合成が成功か失敗かとわかるような状況でした。CG全盛の現代でも、それこそサイテーでヘタクソな特撮映画は数多く作られておりますが、そんな中で「どうやって撮影したんだ?」と思わせる映像を1921年に作ってしまったキートン、レスリー、ガブリーとは一体何者だったのでしょうか。ただただ驚嘆するばかりです。
この技術の偉業にとどまらず、特にキートンの作家性までも考証しますと、このマスク合成をカット割り(編集)と併用して、《劇場の上階と下階で起こるケンカ》まで描写しているので、ビックリ度はさらにアップします(写真B)!この演出は、上下の位置関係と時空間の応酬がマルチ画面のごとく完全にシンクロしてギャグを構成しているのです!
――――― 後篇に続く