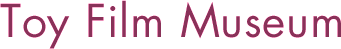2018.05.23infomation
「新野敏也のレーザーポインター映画教室第3弾」のレポート(8)
【第三部:キートン伝説を徹底追及!】
 (A )
(A )
 (B)
(B)
 (C)
(C)
 (D )
(D )
「探偵学入門」(旧題:忍術キートン) Sherlock,Jr.
1924年バスター・キートン・プロダクションズ=メトロ・ピクチャーズ作品(アメリカ)
製作:ジョゼフ・M・スケンク
監督:バスター・キートン、ロスコー・アーバックル
脚本:ジーン・ハヴェッツ、ジョー・ミッチェル、クライド・ブラックマン
撮影:バイロン・ホウク、エルジン・レスリー 、美術:フレッド・ガブリー
照明:デンヴァー・ハーモン、編集:ロイ・B・ヨークルソン
出演:バスター・キートン、キャサリン・マクガイア、ジョー・キートン
ワード・クレイン、アーウィン・コネリー 、フォード・ウエスト
伴奏:谷川賢作とSonorizzano
青木タイセイ(トロンボーン/エレキベース)、太田惠資(ヴァイオリン)
高良久美子(マリンバ/ドラムス)、谷川賢作(ピアノ/キーボード)
HISASHI(ヴォイス・パフォーマンス)、三木黄太(チェロ)
※2001年1月20日(木)アテネ・フランセ「夢の森にて2001」より
日本語字幕:フランチェスコ・サルタレリ
本作は、キートンを知らない人へ最初にオススメするべき逸品でしょう。キートン特有の見事なトリック、アクロバット、パントマイム、マジックが良質のストーリーに隙間なく組み込まれている、まさに代表作だからです。この映画は全編クライマックスのごとく緊張感が漲っていて、見せ場だらけなのです。ここで敢えて出色のシークエンスを挙げるとするならば、前半の《スクリーンの中に入るキートン》、中盤の《ビリヤード》、ラストの《オートバイのハンドルに座り暴走》でしょう。
それでは、未見の人にはネタバレしないようにストーリーを伏せながら、出色のシークエンス3つを説明します。
まず《スクリーンの中に入るキートン》ですが、トリック(特殊効果)につきましては、先の『即席百人芸』でタップリ解説しましたので、本項ではその進化した部分だけを解説します。とにかく本作を見た人の誰もが《スクリーンの中に入るキートン》に驚愕します。このシークエンスは、現代のVFXアーティストやCGクリエイターまでもが、初見で腰を抜かしているくらいです。
仕掛けを簡単に明かしますと、劇場のセットA(スクリーン部分が黒く塗られている)、劇場のセットB(Aの黒く塗った部分を開けて、スクリーン奥が室内セットとなっている状態=あたかも映画の一場面のように見えるライティングが施されている)での展開を、上手に編集で切り替えているのです。

まず、セットAのスクリーン上に、予め作っておいた《映画》をハメコミ合成します(上掲図1)。これは1920年代前半に正式稼働したばかりのオプチカル・プリンター(怪獣映画などで多用される画面合成のフィルム焼けつけ装置)を使って、《映画》が上映されているように見せている訳です(写真A)。

次にキートンが上映中のスクリーンに入る仕掛けでは、セットBに変更します(上掲図2)。このセットAとセットBの転換をいつ行なったのか?実は途中でフィルム編集されているのですけど、この仕上がりがあまりに完璧なため、見ている我々は本当に映写中のスクリ-ンへキートンが入り込んでしまったと驚かされるのです(写真B)。
それからスクリーンの中でキートンは悪夢に翻弄されますが、この部分は予め作っておいた《トリック映画》を、セットAに再びオプチカル・プリンターでハメコミ合成します。
この文章だけでは未見の方が、チープでチャチな子供騙しの合成画像と思うかもしれません。しかし!どこからがセットAで、どこからがセットBなのか?どうやって撮影したのか?などなど、まず見破るには相当な眼力と注意力が必要です。ヒントは、周囲の劇場内にいる観客の動きにあります。
何よりもこのトリックの驚くべき点は、《劇場内をウロウロするキートン》実景と、予め作っておいた《スクリーン内でオロオロするキートン》映像の身長をピッタリ一致させて、どのタイミングで実景と映像を切り替えたのかわからなくする工夫、つまり我々はそのキートンのサイズから錯覚を起こす訳です。因みに、このキートンの身長(またはポーズを)をピッタリ一致させての撮影法は、単に測量機と分度器を使っただけとのことなので、僕にとっては仕上がりのトリック効果よりも、この撮影話の方が衝撃はデカイです!
但し、オプチカル・プリンターを使用していることから類推すると、一部の演技(キートンのポーズなど)は、この機材を併用してトリミングしていることも考えられます。スクリーンの中でのキートンには、ハメコミ合成でサイズを調整したとおぼしきミキレ(本来は画郭の外にある、写ってはダメな部分)が確認できるからです。このヒントは、《スクリーン内でオロオロするキートン》のスクリーン内側ラインの下部に、余白のようなスジが確認できます(写真C)。ワンカットだけ、ほんの一瞬ですヨ。
理屈の上ではこんなカンジで簡単に説明できますが、VFXでパースやサイズや色調やライティングの具合を補正したり、レイヤーを重ねて合成したり、モーフィングを応用してササッとポーズを修正できる現代からすると、1924年にフィルムで完成させたキートンの実写トリックは、やはり神技か魔術以外の何ものでもありません。
現代のVFXと古典フィルムの技術力を比較しても驚かされますが、それより何よりキートンがゼロからの発案でこの特殊効果を完成させたことが一番の驚異でしょう。我々は特撮をやりたいと思えば参考となるウルトラマンやゴジラが存在し、SFを作りたいと思えば『スター・ウォーズ』や『アバター』でVFXを研究することができます。しかし、当時のキートンには参考となる前例がありません。頭で思いついた内容を具現化するには、すべて自力でゼロから開発するしか方法がない訳ですから。
ウディ・アレンが自作『カイロの紫のバラ』で、スクリーンに出入りする主人公のアイデアやテクニックを『探偵学入門』から拝借したのではないか(それともオマージュなのか)とインタビュアーに訊かれ、カンカンに怒って全否定してましたけど、私見では『探偵学入門』の61年後に発表された『カイロの紫のバラ』の方が総体的にヘタクソじゃないかと思いました。訊かれて怒るアレン氏の方が、僕には情けなく見えました。これじゃまるで、パクリがバレて居直っているだけじゃないか!
あと、本作でのオプチカル・プリンター使用のアイデアは、ノン・クレジットで共同監督を務めたとされるロスコー・アーバックルの提案かもしれません。アーバックルは、1916年にキーストン社での自作『でぶと海嘯(デブ君の漂流)』にて、まだ試験運用の段階であった筈のオプチカル・プリンターを使っております(写真D)。この時から8年を経て、キートンの斬新なギャグを実現させるために、この機材を推奨したのでは?と僕は考えました。
次の見せ場は中盤の《ビリヤード》ですが、これはとにかくタネも仕掛けもなく、ひたすらナマで驚愕のテクニックを披露します。編集やカメラ・アングルでキートンをスゴ腕に見せた訳ではなく、すべての技がワンカットで行われます。キートンはビリヤードの腕前がプロ級だったそうで、この事実を隠して賭け試合に臨み、相手が驚くのを楽しんでいたとの逸話があります。
そして、ラストの見せ場《オートバイのハンドルに座り暴走》ですが、これも本当にハンドルの上に座ったままで走行しております。あまりに危険なカットだけは、オプチカル・プリンターの合成、フィルムの逆転、またはオートバイのハンドルを模した移動式セットを併用しておりますが、《スクリーンの中に入るキートン》のトリック同様、実際のスタントとバーチャルな効果がどこで切り替えられているのか? 巧みな編集で、わかる方もそうはいないでしょう。
この《オートバイのハンドルに座り暴走》は、ロスコー・アーバックルの甥っ子で、キートンとも仲の良いコメディアンのアル・セント・ジョンが得意としていた《自転車の曲乗り》から着想を得たのかもしれません。ジョンが自転車のハンドルに座る曲乗り芸は、ジョン自身も主演映画の中で何回か披露しております。
以上の見せ場のほか、キートンが一瞬で老婆の衣装に着替えるアクロバット、小さなアタッシュ・ケースに飛び込んで消えるマジック(この仕掛けについては『レーザー・ポインター映画教室』へご来場下さいました方にだけコッソリ教えました)など、舞台芸人時代にステージで演じていたのであろう技などが、まばたきする間もなく次々と繰り出されます。
また、キートンの実父の助演に加えて、当時の実際の妻、本作の脚本家、プライベートのマッサージ師などもところどころでチョイ役を演じております。既にご覧になっている方はもう一度、初見の方は是非、拙文をご参考にジックリ鑑賞してみて下さい。
最後に、僕が本作のトリックのネタなどを暴き公表するのは、先人の情熱、創意工夫、アイデアの素晴らしさを、改めて皆さんに再発見して頂きたいからです。例えば、ギザのピラミッドの建築工法が完全解明されていても、それが4500年も前に行なわれたことだと知ればビックリする訳で、現在の建築技術と比較すれば一段と古代のロマンも広がりますよね。同様に古典映画には、ロマンとナゾが多く潜んでおり、再上映されない限りは、それが誰からも忘れ去られてしまうのです。そんなフィルムを再見してみると、最先端の技術で作られた映像よりエネルギッシュでパワフルな印象を受けることもあります。そんな調子で、僕は先人の創意工夫や奇想天外な発想をより多くの人に知って貰いたくて、古典映画と向き合っております。