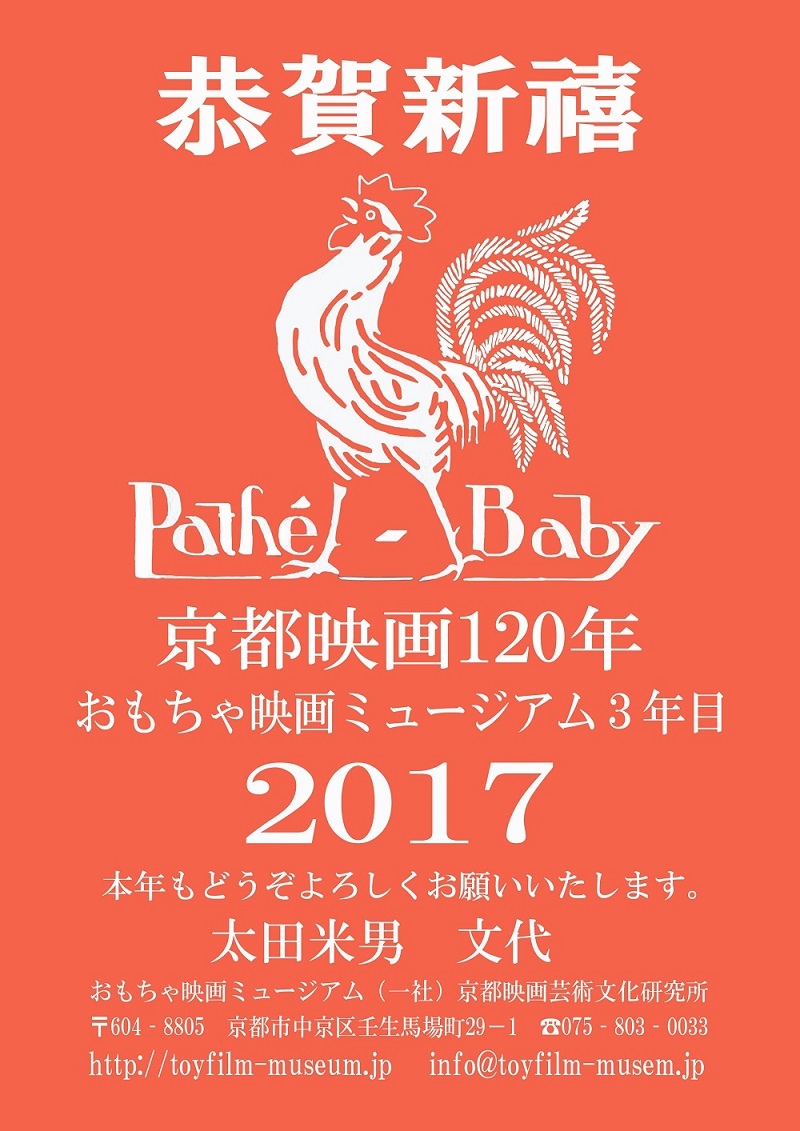2017.01.01column
あけましておめでとうございます‼
皆さま、新年あけましておめでとうございます
穏やかな酉年が始まりました。昨年中は、大勢の皆様に支えていただきながら、いくつもの催しを開催することができました。「頑張っていますね」の声が何よりの支えとなりました。今年も「おもちゃ映画ミュージアムらしい」展開ができるよう頑張ります。引き続き応援を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
 12月26~29日、台北の友人たちに会いに行った折、訪れた行天宮で行列に加わり、いただいたお札。何種類かあり、これはその内の一枚。ミュージアムの玄関、館内にも貼って、賑やかな正月飾りとしました。今年が平安な世の中になりますように‼
12月26~29日、台北の友人たちに会いに行った折、訪れた行天宮で行列に加わり、いただいたお札。何種類かあり、これはその内の一枚。ミュージアムの玄関、館内にも貼って、賑やかな正月飾りとしました。今年が平安な世の中になりますように‼
あらためまして、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます
 初詣は、日付が変わってすぐに、近くの月読神社へ。同行した次男が通った大住中学校のすぐ傍。「懐かしいなぁ」の声に、私も同じように思いました。地域史を研究していたころは夢中になっていた場所の一つです。
初詣は、日付が変わってすぐに、近くの月読神社へ。同行した次男が通った大住中学校のすぐ傍。「懐かしいなぁ」の声に、私も同じように思いました。地域史を研究していたころは夢中になっていた場所の一つです。
そのまま早起きをして、京都市内の世界遺産「東寺」へ。「ひょっとしたら映像関係の掘り出し物がないかと、今年最初の東寺ガラクタ市をうろちょろ。期待は残念ながら空振りに終わりましたが、「早起きは三文の徳」で、美しい初日の出を拝むことができました。
 朝日を見ていると、3年目を迎えたミュージアムにエールを送ってもらっているように感じられ、「頑張らねば」という思いを一層強く抱きました。
朝日を見ていると、3年目を迎えたミュージアムにエールを送ってもらっているように感じられ、「頑張らねば」という思いを一層強く抱きました。
年末までバタバタしていたので、上掲年賀状は今日できたばかり。町家でその作業をする連れ合いに申し訳ないと思いつつ、電車に乗って新田辺駅に戻り、次男の希望で二人京田辺市内の棚倉孫神社(たなくらひこじんじゃ)までウォーキング。大阪の友人に教えられて、地元の社寺に興味を持ったそうな。
 地元の京田辺市内には、延喜式神名帳に載る大社が3つもあります。前述の月読神社のほか、棚倉孫神社もそれだと由緒を語りますが…
地元の京田辺市内には、延喜式神名帳に載る大社が3つもあります。前述の月読神社のほか、棚倉孫神社もそれだと由緒を語りますが…
今日受け取った賀状に「今年は久々に椿井文書(つばいもんじょ)の論文が出る予定です」と綴った研究者からの一枚があったので、それを拝見することが楽しみです。私自身はミュージアム開館以後、地域史からすっかり遠ざかるを得ず、いろんな知識を消失してしまっていることが悔しい。
 続いて、乞われるままに京田辺市薪の酬恩庵一休寺まで足を延ばしました。「トンチの一休さん」 で知られる一休宗純禅師(1394~1481)が、荒れていた堂宇を再興し、後半の生涯をここで送りました。81歳で京都の大徳寺住職となった時も、遠く離れた薪の地から輿に乗って通われました。写真右に菊花の透かし彫りがある門扉。
続いて、乞われるままに京田辺市薪の酬恩庵一休寺まで足を延ばしました。「トンチの一休さん」 で知られる一休宗純禅師(1394~1481)が、荒れていた堂宇を再興し、後半の生涯をここで送りました。81歳で京都の大徳寺住職となった時も、遠く離れた薪の地から輿に乗って通われました。写真右に菊花の透かし彫りがある門扉。
 珍しく門扉が開いていて、一休禅師御廟所を拝見できました。1475(文明7)年、禅師82歳の時に自ら建立され、1481年11月21日に88歳で亡くなった一休さんはここで眠っておられます。美しい枯山水庭園は茶祖・村田珠光作。後小松天皇の皇子なので宮内庁の管轄となっています。
珍しく門扉が開いていて、一休禅師御廟所を拝見できました。1475(文明7)年、禅師82歳の時に自ら建立され、1481年11月21日に88歳で亡くなった一休さんはここで眠っておられます。美しい枯山水庭園は茶祖・村田珠光作。後小松天皇の皇子なので宮内庁の管轄となっています。
 方丈庭園(名勝指定)の作者は、松華堂昭乗、佐川田喜六、石川丈山の合作と伝わっています。
方丈庭園(名勝指定)の作者は、松華堂昭乗、佐川田喜六、石川丈山の合作と伝わっています。
 江戸時代初期の禅院枯山水庭園。先を急ぐ用ができたので、ゆっくり座して拝見できなかったのですが、次男がこうした世界に関心を寄せてくれたことがとても嬉しかったです。台北では、行天宮、清水祖師廟などを見学しましたが、こうして一休寺の侘び寂びの世界を前にして、それぞれの信仰、心のよりどころとしての表し方の違いを興味深く思いました。
江戸時代初期の禅院枯山水庭園。先を急ぐ用ができたので、ゆっくり座して拝見できなかったのですが、次男がこうした世界に関心を寄せてくれたことがとても嬉しかったです。台北では、行天宮、清水祖師廟などを見学しましたが、こうして一休寺の侘び寂びの世界を前にして、それぞれの信仰、心のよりどころとしての表し方の違いを興味深く思いました。
できることなら今年はバタバタせず、落ちついて、心豊かな運営ができるよう心がけたいと思います。酉年最初の思いです。