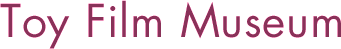2024.07.11column
雨の中を次々と
梅雨らしく雨が降り続いています。シトシトと降るぐらいなら良いのですが、バケツをひっくり返すぐらいに降ると困ります。皆様大丈夫ですか?こんな天候の中ですが、今朝10時半前にお越し下さったのが岐阜県からの女性。第1期の時は「毛利清二の世界~映画とテレビドラマを彩る刺青の世界」をご存知じゃなくて、「近くの京都国立博物館まで来ていたのに、見ることが出来なかった」と悔しがっておられました。岐阜や名古屋から見に来て下さる人が結構おられます。
この女性によると、「岐阜の歓楽街にあった銭湯には、早い時間に行くと何人も刺青を入れた人がおられて、それは普通の光景だった。落語や芝居が好きで、いつも見聞きしながら「(落語や芝居に登場する人物は)どんな刺青をしていたのかしら?」と思っていた。火消しや鳶、飛脚など命懸けの仕事をしている人たちにとって、刺青は自分を鼓舞するためのものであり、万一の時は刺青で誰であるかが判別できた。そういった歴史背景があるので、刺青の絵を見るのを楽しみにしていた」と話して下さいました。
続いてやって来られたのはフランスのパリからお越しの女性2人。6月25日フランス国立極東学院(EFEO)での講演会講師を務められたクロード・エステーブさんのお知り合いのコリーヌさん(向かって左)とナディアさん。刺青の下絵だけでなく、おもちゃ映画などの展示や拙い話も面白がって聞いて下さいました。丁度1年前にルアネックからお越しのCarmina Lecarpentierさんが、私の依頼を受けて当館の案内リーフレットのフランス語訳をしてくださいました。そのリーフレットと元になった日本語版を手にして下さっていたので、それが嬉しくて写真を撮りました。

昨年はフランス西部のニースで明治時代の日本の刺青をテーマにした展示が行われ、今は10月までフランス東部のランスで開催中です。来年はフランス南部のカルカソヌ市で開催される見込みです。来年のカルカソヌ市での展覧会時に毛利さんの下絵も展示したいという希望がEFEOのクリストフ・マルケ先生(下掲写真左)経由で寄せられていることなどを話していたら、丁度当該映画関係者の方が東京から展示を見に来館。他所者の気楽さで「毛利さんのフランス行きや海外の人が刺青下絵をご覧になっている反応を撮影してドキュメンタリーにすればいいのに」などと話しました。さて、今夕の毛利さんを交えての話し合いはどうなったかしら?

これは6月30日毛利清二さんがお越しになるというので連絡を差し上げたら、急いで駆けつけて下さったクリストフ・マルケ先生とクロード・エステーブ先生(下掲写真右)。エステーブ先生は写真家で初期の日本写真を収集し、その研究家。お二人とも毛利さんの話を真剣に聞いておられます。一生懸命メモを取っておられるのは、今回の展覧会提案者の山本芳美・都留文科大学教授。

私が右手に持っているのが6月25日のチラシ、左手に持っているのがランスで開催中の展覧会の図録。フランス語なので中身が分からずもどかしいのですが、その後お越しになったフランス人の方に部分をかいつまんで教えて貰いました。明治時代に刺青が禁止された後の1876年に日本の宗教に関する科学使節団を率いてエミール・ギメが来日し、画家のフェリックス・レガミに同行して日光へ行く途中で、刺青をしている飛脚を見て描き、戸塚訪問中にも、仕事中の刺青師のスケッチもしたと証言しています。ランスにいたHugues Krafftという人物(シャンパンのお金持ちの息子、1853-1935年)は刺青を撮った写真だけでなく、水彩画でも記録して本にしています。
連れ合いに聞きますと、初期の写真や映画のフィルムの感光乳剤は、戦後にパンクロマチック(可視光域がすべて映る全整色)フィルムができるまでは、赤が再現できず、赤い色は黒く映りました。血色の良い人ほど黒く映りました。それで無声映画時代は男優でも白塗りの化粧をしていました。写真乳剤の歴史が、化粧品や照明手法にも影響を与えたと申しています。撮った写真はモノクロ写真に手彩色されましたが、本来の色鮮やかさにはならないので、写真だけでなく水彩のスケッチ画も残したのでしょう。その珍しく貴重な写真と水彩画によって、当時の刺青の様子が分かります。
横浜では外国人向けの刺青のサービスがあり、中でも有名だったのは彫千代。英国のジョージ4世も1881(明治14)年に彼によって腕に龍の刺青を入れました。画家の藤田嗣治は自分の左腕に腕時計の刺青を入れていたほか、彫千代の見本図コレクションを持っていたそうです。このコレクションは、秋田県立美術館に行くとみられる?https://www.akita-museum-of-art.jp/contents/data/event_sys/5c870f222916e.pdf
ロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世も1891(明治24)年に長崎で右腕に龍の刺青をいれていて、文明開化を急ぐ明治政府が1872(明治5)年に欧米人の目を気にして禁止した刺青は、逆に海外からの評価が高かったのです。京都には彫ヤス(本名中島)という彫り師がいて、英語で広告も出していたそうです。バジル・ホールという人は、「イギリス人より日本人の彫師が上手だ」と紹介もしていたとか。19世紀の終わり、外国人が日本に来て、日本土産に刺青を持ち帰りました。日本の刺青禁止政策は終戦直後の1948(昭和23)年まで継続します。

講演やフランスのニースでの上掲展覧会図録を見ていて、どこかの骨董市で1枚でも明治の日本人の刺青姿を撮った写真はないものかと思って探しましたが、それらはお土産として海外にこそ残っていたので、日本で見つかるのは滅多にないことなのだと、当たり前のことに漸く気が付きました。毛利さんにフランスの図録をお見せしたところ「立派だけど、映画的ではないので参考にはならない」との返事。
また、1880年代の右肩から腕にかけて龍の刺青が入った女性が右肩を脱いで徳利とお猪口を持つ写真も目を惹きますが、写真を撮るために描いたものかもしれません。山本芳美先生によれば「女性が刺青をしていたのは10人に1人もいない。いたら記事になったぐらい」だそうです。男性に彫った写真をみても、絵で補ってくっきりさせているものもあります。世界中を旅して回ったHugues Krafftは1882(明治15)年~1883(明治16)年に日本を訪問し、ガラス乾板を使用して撮影するツァイスのカメラを用いていたので、野外での撮影ができました。残された写真や水彩画から、江戸時代から明治10年代の刺青がイメージできますね。

ランスで開催中の図録にクリストフ・マルケ先生の論文も掲載されていて、そこに載っていたHugues Krafftが用いていたカメラ。乾板写真。講演では日本最初期の写真家、下岡蓮杖(1823-1914年)についても話がありました。彼は湿板写真の技術を習得し、1862(文久2)年から横浜で写真館を開業しています。彼は画家でもあったので、鶏卵紙にプリントした写真に、自分で彩色もしていました。「横浜写真」といわれるように横浜には多くの写真館があり、幾人かの狩野派の画家が周りにいて彩色していたかもしれないとのこと。下岡のカメラは小さく、写真も小さかったそうです。下岡が使っていたカメラは、こちらのサイトに載っています。https://www.shimoda-museum.jp/ippin/2019/10/10/1348/
「横浜写真」も海外にお土産に持ち帰られているので日本では見つかることが少なく、当館で展示しているものも海外から入手しました。

表面の駕籠かき。写真館のスタジオでモデルを置いて撮影したものでしょう。プリントした後で手彩色しています。

裏面は洗面をする女性ですが、ニースやランスの図録に掲載されている前述の脱いだ右肩から腕にかけて刺青が入っている女性の写真と似た雰囲気ですが、刺青は入っていませんね。駕籠かきのほうも褌姿ではなく、刺青も入っているのか否かわかりません。土産用に写真館のスタジオで日本らしく演出した写真のように思います。あとの2枚も、唐人お吉の写真の裏には鎌倉大仏の写真が、三人の女性がだらしない恰好で蕎麦を食べている写真の裏にはどこかのお寺の写真があって、観光写真とセットに日本の風俗を演出して写し、日本土産にしていたものと思われます。逆に言えば、海外の人は、そういう眼差しで明治の日本を見ていたのだなぁと気付かされます。当館の「横浜写真」については、イタリアの写真家で横浜を拠点に写真スタジオを構え、日本の旅行ガイドブックを最初に出版したアドルフ・フォルサーリ(1841.2.11 —1898.2.7)が撮影したものではないかとみています。
さて、「仁侠映画が好きで全部見てきた」という人が先日の女性のお客様に続いて、今日もお越しくださいました。井上将一さん(76歳)。会場には『極道戦争 武闘派』(1991年、中島貞夫監督)で火野正平さんに描いた「張順 水門破り」の下絵がありましたが、本当は『侠客列伝男』(1971年、山下耕作監督)で伊吹五郎さんに描いた水滸伝三十星・波切張順を見たかったのだそうです。「何で?」とお聞きしたら、今『水滸伝』を読んでいるからだそうです。

私は、中国明代に書かれた長編の『水滸伝』も読まずに、月岡芳年が晩年に描いた浮世絵「月百姿」シリーズ100枚のうちの1枚、「九紋竜」の版画を先日買って展示の隅っこに飾っている浅はかさ。よく見たら、前掲フランスのニースでの図録表紙が三代歌川豊國の「九紋龍支進」でした。
掲示している俳優高橋英樹さんのメッセージに「仁侠映画が全盛期の1960年代から70年代は安保闘争が起き、人のために命を落とすことを美徳とするような空気感がありました。仁侠映画はそのような時代背景の中で生まれ、登場人物の背中に描かれた刺青は、弱きを助け、強きをくじき、義のためには命も惜しまないといった生き方の象徴だと思います。現代の若者には考えられないような生き方かもしれませんが」とあります。
井上さんと話をしているところに、写真家、ジャーナリスト、編集者としてご活躍の都築響一さんが東京から来館。毛利清二展のことはもとより、私どものミュージアムと活動についても取材して頂きました。近日掲載されるようですので、その時はまたお知らせします。ミュージアムの雰囲気を面白がってくださいました。毛利清二展が契機になって、多くの媒体で会場となった私どものミュージアムも広く知って頂ける機会となりましたので、そのことを山本先生始め関係者の皆様に心から感謝しています。
その後お越しの若いカップルの男性は、まだ線彫りのような刺青でしたが、入れたくて入れたくてたまらない風で食い入るように下絵に見入っておられました。なんだか急に母親になったような気になって、自分なりにちょっと諭しました。3か月近く、いろんな方の刺青を見てきて、それぞれの方の自分表現だと思ってきましたが、まだ私にもそうした違う視点があるのかと己が内心を垣間見たような気がしました。